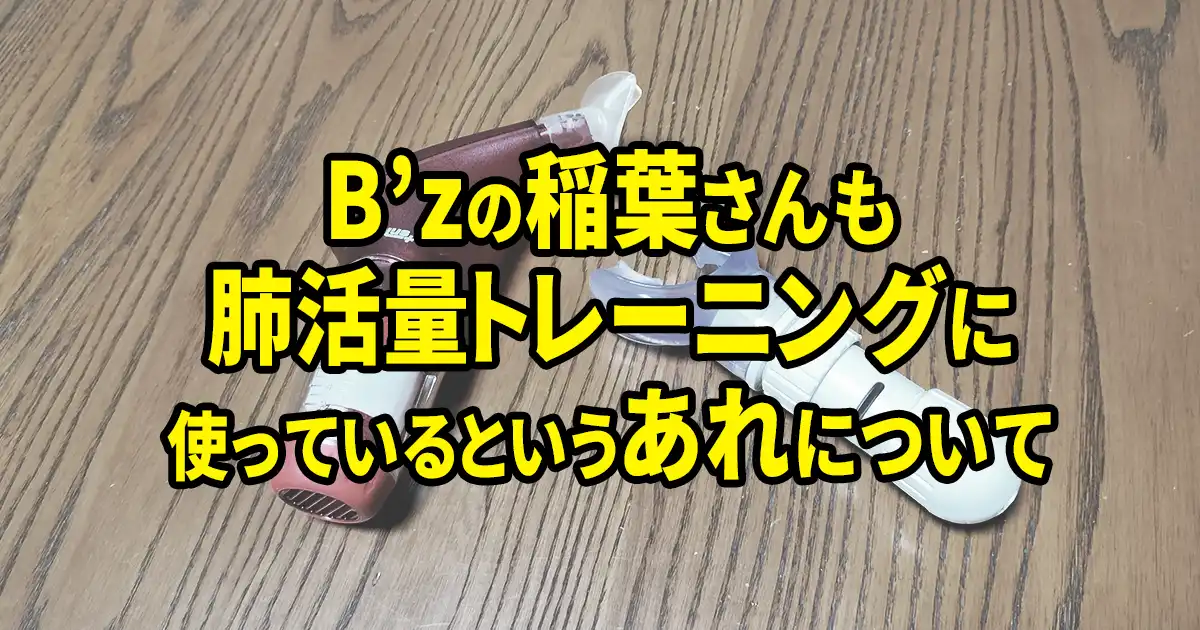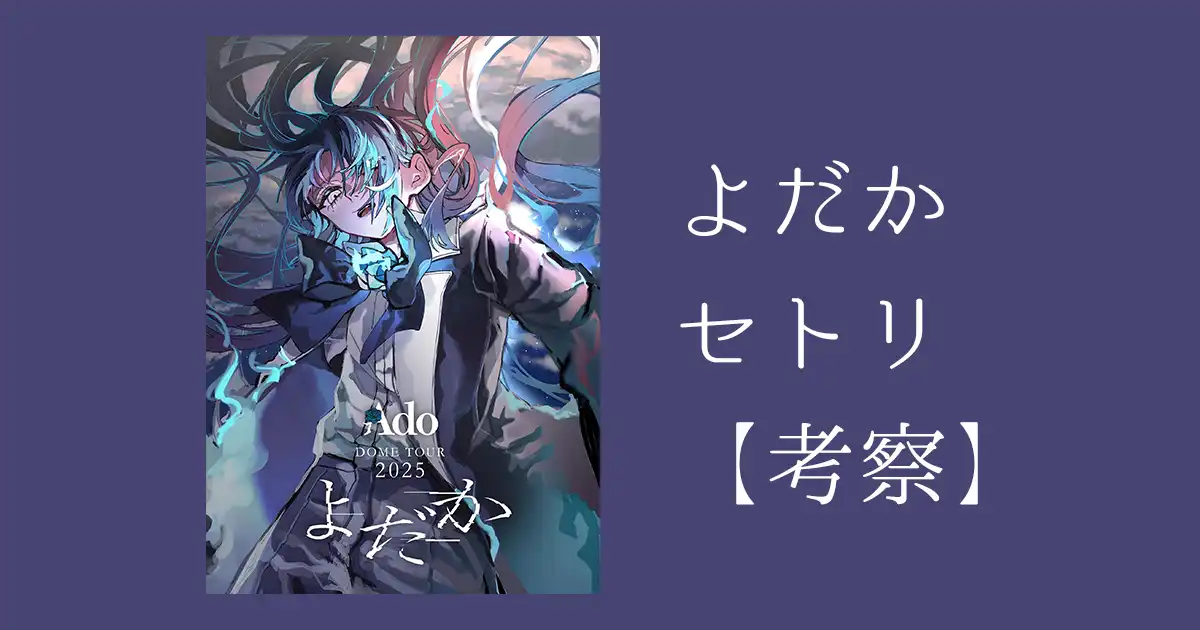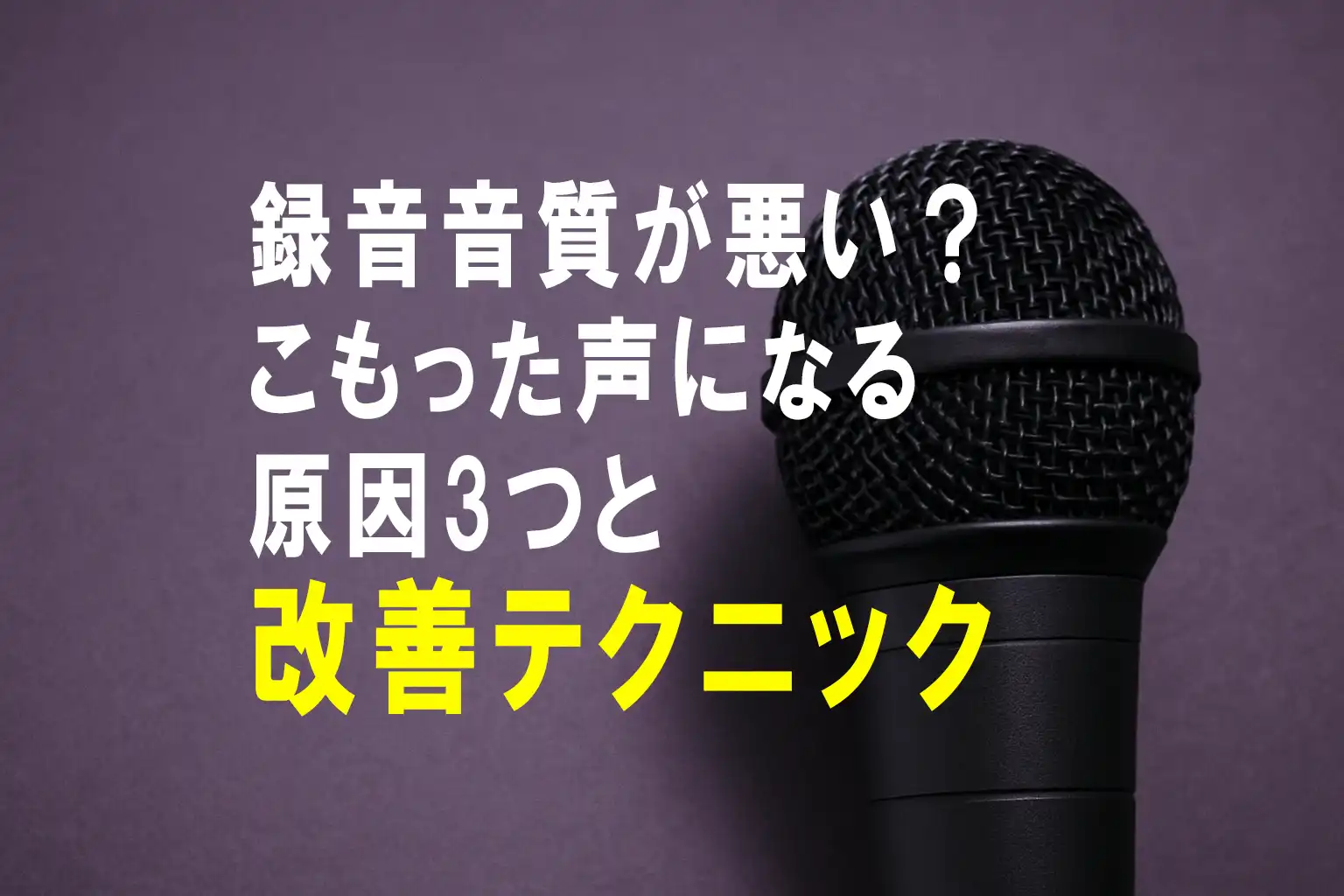
「録った声がモワッとして抜けない…」――原因はだいたい3つに絞れます。
難しい理屈より、“いまから直せること”を優先してまとめました。
目次
マイク・録音機材の問題
マイクの向き・距離がズレている
まずはここを直すだけで世界が変わります。
- 口〜マイクは10〜15cmを基準(声量が大きい曲やシャウト気味なら15〜20cmに後退)
- カプセル正面を口へ。ロゴ面や矢印の向きを確認
- ポップ対策は10〜20°だけオフ軸+ポップガード(口から5〜8cm)
補足
マイクを近づけるのが“悪”ではありません。狙いの音になる距離を探す作業が大事です。近づくほど近接効果で150〜300Hzが持ち上がり、こもりやすくなります。
マイクの“性格”が合っていない
「安いから高域が出ない」という話より、周波数特性と指向性の相性が本質です。
- 2〜5kHzが落ち込み気味の個体は明瞭度が出にくい
- カーディオイド等の指向性マイクは近距離で低域が膨らみやすい
- 必要ならHPF(80〜120Hz)で低域を軽く整理、8〜10kHzを+1〜+2dBで“空気感”を少し足す
おすすめのマイク⇓
LEWITT ( ルーイット ) / LCT 440 PURE レビュー
抜け感が良くクリアだとなかなか好評です、リンクのレビューもなかなかに好評です。
入力レベルと最低限の下ごしらえ
- ピーク -12〜-6dBFSに収まるようにゲイン調整
- 録音は48kHz/24bit WAV推奨(後処理の余裕が増える)
録音環境の影響
小部屋の反射と定在波が“もやり”を作る
壁・窓・机天板など硬い面の初期反射で明瞭度が落ち、狭い部屋は100〜300Hzが膨らみがち。
すぐできる対策
- マイクの背面と片側面に吸音(厚手の布、服が詰まったクローゼット、リフレクションフィルター)
- 壁から30cm以上、机天板からも距離を取る
- 床にラグを敷く
- 位置を前後に20〜30cm動かして、低域の膨らみが薄い場所を探す
EQは“最後の微調整”
環境とマイキングで土台を作ったうえで、200〜400Hzを-2〜-3dBだけ削って濁りを整えるのが安全です。先にEQで大きくいじると不自然になりがち。
歌い方(発声)の影響
明瞭度は“前に飛ぶ”成分で決まる
聞き取りやすさは2〜5kHzの子音・輪郭の帯域がカギ。ここが出ていないと「抜けない声」になります。
通りを良くする簡単ドリル(1分)
- 軽くハミングして鼻腔の振動を感じる
- その響きを保ったまま口を開ける(抜けが落ちないか確認)
- 仕上げに顎を少し下げ、口の容積を確保して曇りを防ぐ
- “鼻声”になりすぎたら戻す――軽く鼻腔を使うがコツ
たとえば、アニメの“前に飛ぶセリフ”をイメージして少しだけ鼻に抜くと、マイクに乗る感覚を掴みやすいです(やりすぎ注意)。
付録:後処理は薄味が正解
- NR(ノイズ除去)*は最小限。かけすぎると高域が欠けて一気にこもります
- De-Esserは6〜8kHzを2〜4dBだけ。巻き込みに注意
- コンプはAttack 15〜30ms / Release 60〜120ms / GR 3〜6dBで子音を潰さない
- ステレオ素材をモノ化する前にL/Rの遅延・極性を確認(位相ズレは高域が消えます)
すぐ確認できるチェックリスト
- 正面アドレス、10〜15cm、10〜20°オフ軸、ポップガード5〜8cm
- HPF 80〜120Hzオン
- ピーク-12〜-6dBFS
- 200〜400Hz -2〜-3dB(必要時のみ8〜10kHz +1〜+2dB)
- NR/De-Esserは薄味
- 背面・側面を吸音、壁/天板から距離
- モノ化前に位相チェック
まとめ
こもりの三大要因はマイキング/部屋/発声。
まずは向き・距離と背面吸音、それでもダメなら200〜400Hzをちょい引き。